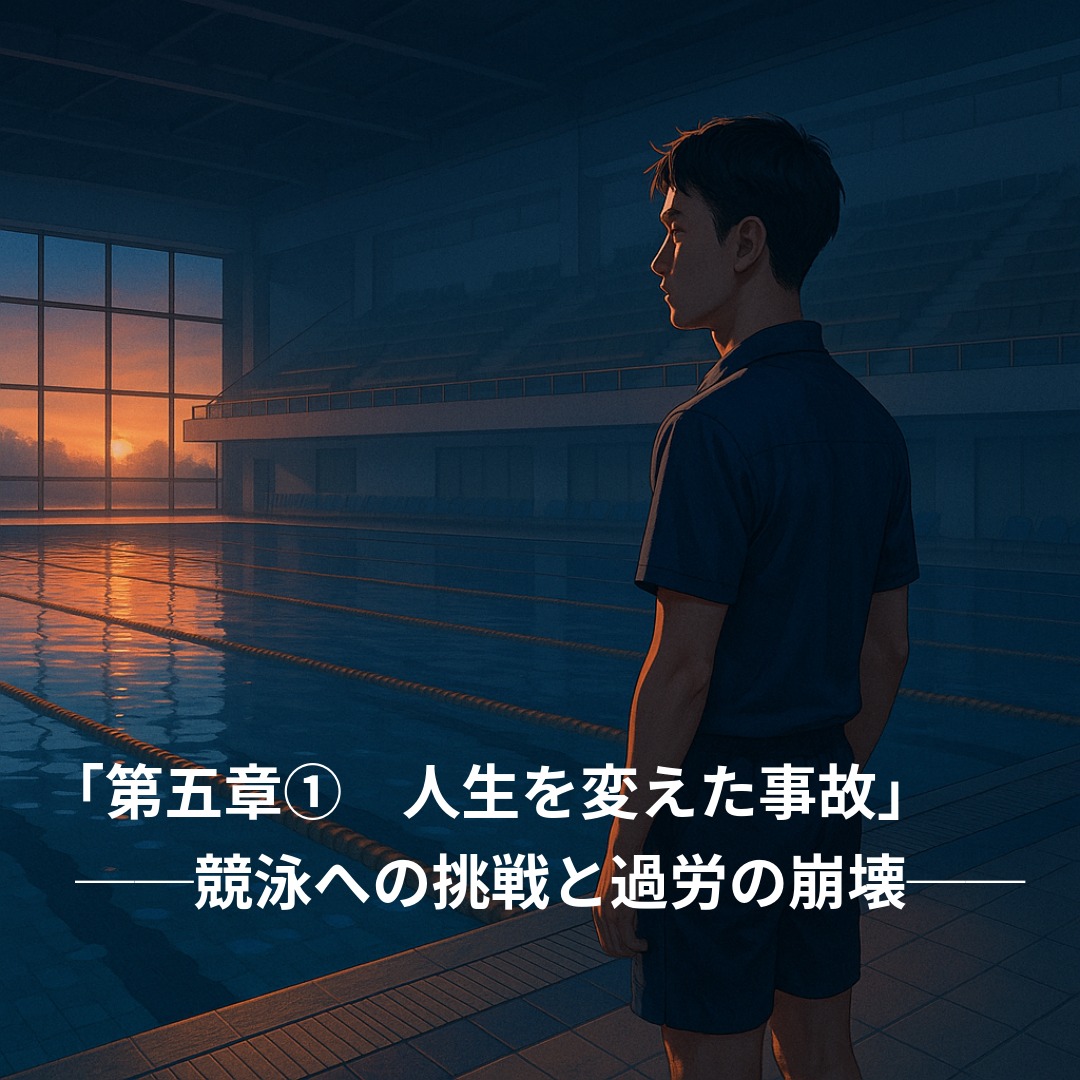ブログBLOG

『骨について②』
-骨折の種類を知る-
皆さまこんにちは、おくがわ整体院スタッフ 及び TC研究会 理学療法士の梅澤です。
本日もコラムに興味をもって頂き本当にありがとうございます。
今回のコラムの内容は前回に引き続き『骨について』で、骨折のことを中心にお話させて頂きたいと思います。
私のこれまでの急性期病院での経験も含め、やはり早いうちから体を大事にしていく習慣をつけていくことが重要かと思っております。
これは私のどのような経験からかというと、急性期病院時代に関わってきた患者さんのことで 例えば 脳卒中 心筋梗塞 変形性~症 脊柱管狭窄症 慢性閉塞性肺疾患(COPD) 糖尿病による下肢切断 骨粗鬆症による骨折 などなどもっとありますが この様な病気などにより命の危険にも脅かされた上 手術も必要になったりしてきた患者さんのリハビリをしてきました。
治療後でさえ助かったという安堵感に加え、その後の生活にかなりの支障をきたしてしまいます。 そのため全員とは言いませんが殆ど患者さんが『私の何が悪かったのだろうか?』時にはかなり高齢の方などは『何かばちがあたったのか?』などと思っている方もいらっしゃいました。
さすがに若い方の場合は生活習慣が原因だということを皆さん理解はしておりましたが。 但し、これだけ科学的なことがわかってきている世の中でも中々 生活習慣は変えられないというのが難しいところではあります。これに関しては社会的な問題が大きいということが認識できます。
少し話が飛躍しすぎたかもしれませんが、若い方で脳卒中や心筋梗塞で緊急入院する方などの多くの患者さんは、 仕事しながら口に食べ物を詰め込む様にして食事をしたり 仕事をしていてお腹がすいた時に食事ができずその後に暴飲暴食してしまったり 毎食ファーストフードやコンビニ食 であったり これはほんの例えではありますが 何のために仕事をしているのか 感覚が麻痺してしまっていることもあるのではないかとも思います。
もちろん仕事も食べるためにやっているのですが、それがきっかけで重大な病気になってしまっては本末転倒ですよね。
本来は我々は生きるために食事をしていますよね。仕事のために食事をしているわけではないですよね。 これは少し大げさに聞こえるかもしれませんが、私たちの身体は思っている以上に繊細にできているので、この様な積み重ねが効いてくるのだということをとても実感しています。
ここで特に言いたいことは、病気などが大きければ大きいほど 身体だけは一生ずっと離れることができない かけがえのないパートナー だということがわかるということです。
そのため身体の声を素直に聞いてあげることがとても重要なのではないかと思っています。 感じれるということですかね。
そして骨についても同様のことが言えて、前回の内容でもお話させて頂いたように 骨も日々変化しているため 普段からの生活の影響や体の感覚をきいたり感じることで色々と予防できたり良くすることできるということです。
(今回の病気の例に関しましては元々遺伝的に何かあってなどということは除いてですし、高齢になるとある程度はリスクはもちろん高くなっていくので、その辺は考慮して読んで頂ければ幸いです。
そして、病院でできることは沢山あるので あくまでも病院を使う前段階の体との関わりという感じで読んで頂ければと。)
だいぶ話がそれましたが、今回の内容は 骨についてで 前回の内容では骨粗鬆症についてのお話もさせて頂きました。 この症状になると骨がもろくなり骨折などをしやすくなってしまいます。
本当にもろくなってしまうと脊椎の骨が いつ折れたのかわからないという状態“いつの間にか骨折”などとも呼ばれますが それにより脊髄神経まで障害が出てしまうこともあります。
さすがにここまでの状態になるというのは、かなり高齢であったり何かしらの問題 例えば薬剤性であったり 子供時代からの食生活 子供を沢山生んだ などそれ相応の原因もあることが多いです。
それではここから今話しにも出た骨折について少し理解して頂こうと思います。
骨折には色々な種類があり、分類の方法によって沢山あるので簡単に代表的なものを挙げさせて頂きます。
まずは原因による分類では、以下の3つがあります。
・外傷骨折:外傷によるもので交通事故やスポーツなどでぶつかったりして受傷。
これが最も知られている一般的な骨折と言えます。
・疲労骨折:スポーツなどで同じ部位に何度も衝撃が加えられておこる。
よくあるのが若い人が成長期などで骨自体が変化している時期であった
り、骨以外の様々な部位に栄養が取られてしまい骨が弱っているときに
偏った運動などで集中的にある箇所に負担がかかりすぎて骨折してしま
う状態。
・病的骨折:何かしらの原因で骨がもろくなってしまい、軽い外力で骨折してしまう
骨粗鬆症やがんなどによるもの。
開放性による分類
・単純骨折:閉鎖骨折とも言い、骨が体の中から外に出ないもの
・複雑骨折:これは開放骨折と言い、勘違いしている方もいるかもしれません。
受傷時に骨が体の外に出てしまった状態の骨折を言い、重要なことは感染の問題であり、受傷後は必ず洗浄しなければなりません。
よく肺なども誤嚥性肺炎が問題となりますが、これらの一番の問題は体の中のきれいな状態の部位が外のきたない菌に感染させられてしまうことなんです。
コロナの問題もこれが大きいわけですよね。
ちなみに3つ以上に骨が骨折してしまうことを粉砕骨折などと呼びます。複雑骨折ではありませんのでしっかり違いを覚えておくと勘違いしないですみます。
完全性による分類
完全骨折:骨が完全に連続性を失っている状態を指します。
不完全骨折:よくひびというのがこの状態です。
かなり大雑把なくくりで以上のような分け方ができます。
この中でもまず注目しなければならないのは、原因による分類です。
なぜならばここに関しては、場合によっては早期に発見できたり気づくことで後々クライアント自身で気をつけることもできたりするからです。
外傷骨折は最も一般的なものなので問題ないと思います。
わかりづらいのが疲労骨折と病的骨折かと思います。
病的骨折は、骨粗鬆症や骨腫瘍により骨の強度が弱くなったために、小さな外力で生じてしまう骨折です。骨粗鬆症による病的骨折のことを「脆弱性骨折(ぜいじゃくせいこっせつ)」と呼びます。
この場合の小さな外力とは、立った位置からの転倒またはそれより小さな外力です。
疲労骨折は、通常は骨折を起こさない程度の外力が長期間にわたって繰り返し負荷され、健常な骨が徐々に損傷する状態です。
スポーツ選手の下腿や足部の骨によく発生します。
また、高齢者では普通の生活の中での小さな外力の繰り返しにより、疲労骨折の形態として発生する脆弱性骨折もあります。
少しわかりづらいかもしれませんが、脆弱性骨折というのは様々な原因から起こりはしますが、骨が弱くなって起きているということは間違いがないので、この様な可能性で骨折している場合は、まず骨密度などを確認しておくことも必要かと思います。
そして、その結果によって対策を考えれば良いと考えます。
例えば、骨密度が低ければそれに対する対応として食事及び薬などが必要で補助として適切な運動なども必要となるでしょう。
また、骨密度は問題なく疲労骨折のような形態のみのものであれば、通常の生活の中の問題が大きいのでそれを見直さなければならないでしょう。
スポーツによるものであれば休むだけでなく、その人の動き方の問題の改善が必要でしょうし、スポーツ以外であれば靴の問題や歩行距離の問題、そして一番は体全体の使い方が悪くなってきて、ある特定の部位にばかり負担がかかるようになっていることも考えなければなりません。
この辺に関しては何か一つだけが原因ではなく、色々なことが複雑に絡んでいることもあるので決めつけるのではなく、柔軟に観察することが重要にもなると思います。
最初のところでもお話しましたが、自分の感覚も重要で継続的に見てあげることが必要だということです。
前回のコラムでも述べましたが、骨は日々変化しているので日々変化をしているということを理解してあげなければなりません。
本日もコラムを読んで頂き本当にありがとうございました。
次回は 骨折の回復条件 などについてお話したいと思いますので、興味がありましたら読んで頂ければと思います。

梅澤拓未先生
理学療法士として、急性期病院・認知症専門病院,片麻痺リハビリ専門クリニックなどで13年勤務。
資格
理学療法士
呼吸療法認定士
認知症ケア専門士
介護支援専門員(ケアマネージャー)
福祉住環境コーディネーター2級
日本コアコンディショニング協会マスタートレーナー